歓迎会の司会を任されたけれど、「進行はどうすればいいの?」「台本なんて作ったことがない」と不安に感じていませんか。
開会から閉会までの流れを通しで使えるフル台本、すぐに使えるシーン別セリフ例、さらに場を盛り上げる余興アイデアまでまとめました。
リアル開催はもちろん、オンラインやハイブリッド形式の進行ポイントもカバーしているので、どんな状況でも安心です。
「司会なんて初めて」という方でも、この記事を読むだけで全体の流れがつかめ、当日の進行に自信が持てるはずです。
準備から本番まで、司会者が知っておきたいコツを押さえて、温かい歓迎会を成功させましょう。
歓迎会の進行どうする?2025年版の基本ポイント
歓迎会の進行を任されたときに最初に気になるのは「どんな流れで進めればいいのか」ということですよね。
ここでは、2025年の最新スタイルに合わせて、司会者として知っておきたい基本ポイントをご紹介します。
司会者の役割と心構え
歓迎会の司会者は、単なるアナウンス係ではありません。
会全体の雰囲気を整え、主役が安心して過ごせる場をつくることが最大の役割です。
たとえば、少し緊張している新メンバーを優しく紹介したり、次の挨拶につなぐときに一言添えるだけで、場の空気がぐっと和らぎます。
「自分が楽しみながら進める」という気持ちを持つと、自然と参加者の笑顔も増えます。
| 司会者の主な役割 | 具体例 |
|---|---|
| 進行の管理 | 予定時間を意識して挨拶を切り替える |
| 雰囲気づくり | 和やかな一言を添えて空気を柔らげる |
| 参加者への配慮 | 話す順番を示し、不安そうな人にフォローを入れる |
リアル・オンライン・ハイブリッド開催の違いと注意点
最近では、現地に集まるスタイルだけでなく、オンラインや一部だけオンライン参加のハイブリッド形式も増えています。
リアル開催では声量や立ち位置が大切ですが、オンラインでは接続確認や画面共有の準備が欠かせません。
ハイブリッドの場合は、現地参加者とオンライン参加者が同じ体験を共有できるように工夫することが求められます。
たとえば乾杯のタイミングでは「画面越しの皆さまもご一緒にどうぞ」と一言添えると、全員が取り残されずに参加できます。
| 開催形式 | 注意点 |
|---|---|
| リアル開催 | 声の大きさ・立ち位置・進行テンポを意識 |
| オンライン | 接続テスト・音声確認・進行画面の準備 |
| ハイブリッド | 現地とオンラインの両方に声をかける配慮 |
歓迎会の基本的な進行の流れ【完全ガイド】
歓迎会にはある程度決まった流れがあり、それを押さえておくだけで司会はぐっと楽になります。
ここでは、開会から閉会までの一連の進行と、それぞれの場面で使える例文をご紹介します。
開会宣言と司会者あいさつの例文
開会のことばは会のスタートを印象づける大切な一言です。
緊張していても、ゆっくり落ち着いて話すと場の空気が安定します。
例文(フルバージョン)
「皆さま、本日はご多用のところお集まりいただき誠にありがとうございます。
これより2025年度〇〇株式会社の歓迎会を始めさせていただきます。
本日の司会を務めます、△△と申します。
最後までどうぞよろしくお願いいたします。」
主催者・上司のあいさつを紹介する例文
司会者は紹介役に徹し、終わったあとにお礼を添えるのが基本です。
「それでは、〇〇部長よりごあいさつをいただきます。部長、よろしくお願いいたします。」
挨拶後は「〇〇部長、ありがとうございました。」と一言添えましょう。
乾杯の音頭を盛り上げる司会例文
乾杯は雰囲気を切り替える大事な瞬間です。
参加者が一斉に動きやすいように合図を入れると進行がスムーズです。
「続きまして、乾杯のご発声を〇〇課長にお願いいたします。皆さま、ご準備をお願いいたします。」
食事・歓談タイムでの声かけ例文
歓談時間は交流を深める大切な時間です。
「それではしばらくの間、ご歓談をお楽しみください。新しい仲間とも、ぜひお気軽にお話しください。」
新入社員・転入者の紹介フル例文
紹介は緊張をやわらげながら進めるのがポイントです。
例文(フルバージョン)
「ここで、本日から新しく仲間に加わられた皆さまをご紹介いたします。
まずは〇〇さん、一言ご挨拶をお願いいたします。」
(新メンバーのあいさつ)
「〇〇さん、ありがとうございました。」
既存社員からの歓迎メッセージ紹介例文
迎える側のひとことがあると雰囲気が温かくなります。
「続いて、□□さんから新しい仲間へ歓迎のメッセージをいただきます。」
余興・ゲームの案内例文
余興やゲームは場の空気を和ませるスパイスです。
「ここで、皆さまに楽しんでいただけるよう簡単なゲームをご用意しました。どうぞご参加ください。」
中締め・閉会宣言フル例文
終盤は会全体をしっかりまとめるイメージで進めます。
例文(フルバージョン)
「そろそろお時間となりましたので、中締めのあいさつを〇〇課長にお願いいたします。」
(中締めあいさつ後)
「〇〇課長、ありがとうございました。
これをもちまして本日の歓迎会を閉会とさせていただきます。
皆さま、本日は誠にありがとうございました。」
| 進行場面 | 司会の役割 | 例文ポイント |
|---|---|---|
| 開会宣言 | 会のスタートを告げる | 名前を名乗り安心感を与える |
| 乾杯 | 参加者を一斉に動かす | 「ご準備をお願いします」で合図を出す |
| 閉会 | 会をしっかり締める | 「ありがとうございました」で全体をまとめる |
初心者でも安心!司会進行を成功させるコツ
司会が初めてでも、いくつかのコツを意識すれば安心して進められます。
ここでは、実際に役立つ具体的な方法と、その場で使える短い例文をご紹介します。
準備とリハーサルの重要性
進行表や台本を用意しておくと、自信を持って進められます。
リハーサルは成功のカギであり、声に出して読むだけでも効果があります。
「本番前に一度流れを通しておくと安心です。」
声の出し方・話し方のポイント
声は大きすぎず小さすぎず、会場の後ろまで届くイメージで話します。
早口にならないように気をつけ、語尾をはっきりさせましょう。
「皆さま、どうぞごゆっくりお過ごしください。」
アイコンタクトとジェスチャーの使い方
視線を参加者に向けると、会場が一体感を持ちます。
紹介するときは軽く手を差し伸べて方向を示すとわかりやすいです。
紙を見続けず、時折顔を上げることを意識しましょう。
予定外トラブルへの対応例文
挨拶が長引いたり進行が遅れた場合も落ち着いて対処しましょう。
例文
「予定より少し押しておりますので、この後の進行を調整して進めさせていただきます。」
こう伝えるだけで、参加者も安心して待てます。
緊張をほぐす一言例文
緊張は誰にでもあるものです。
あえて一言添えると空気がやわらぎます。
「少し緊張しておりますが、皆さまとご一緒できてうれしいです。」
この一言で会場が和み、司会者自身も気持ちが落ち着きます。
| 場面 | ポイント | 例文 |
|---|---|---|
| リハーサル | 声に出して練習 | 「一度通して読んでみます。」 |
| 話し方 | ゆっくり・はっきり | 「どうぞごゆっくりお過ごしください。」 |
| トラブル対応 | 落ち着いて進行 | 「この後の流れを少し調整いたします。」 |
そのまま使える!司会進行フルバージョン台本
ここでは、開会から閉会までの流れを通しで使えるフルバージョン台本をご用意しました。
そのまま使ってもよし、自分の会社やチームに合わせてアレンジしても使えます。
開会から乾杯までのフル例文
「皆さま、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。
これより2025年度〇〇株式会社の歓迎会を始めさせていただきます。
本日の司会を務めます△△と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、最初に〇〇部長よりご挨拶をいただきます。部長、よろしくお願いいたします。」
(部長あいさつ後)
「〇〇部長、ありがとうございました。
続きまして、乾杯のご発声を〇〇課長にお願いしたいと思います。
皆さま、ご準備をお願いいたします。」
(乾杯のあと)
「それでは、どうぞごゆっくりお楽しみください。」
歓談から新入社員紹介までのフル例文
「ただいまよりしばらくの間、歓談のお時間とさせていただきます。
新しい仲間とも気軽にお話しください。」
(20分ほど経過後)
「ここで、新しく仲間に加わられた皆さまをご紹介いたします。
まずは〇〇さん、一言ご挨拶をお願いいたします。」
(新メンバーあいさつ後)
「〇〇さん、ありがとうございました。」
(続けて他の新メンバーも紹介)
余興・ゲームから中締めまでのフル例文
「ここで、場をさらに和ませるために簡単なゲームをご用意しました。
皆さま、ぜひご参加ください。」
(ゲーム終了後)
「ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
それでは、そろそろお時間となりましたので、中締めのあいさつを〇〇課長にお願いしたいと思います。」
(中締めあいさつ後)
「〇〇課長、ありがとうございました。」
閉会と二次会案内のフル例文
「これをもちまして、本日の歓迎会を終了とさせていただきます。
皆さま、本日は誠にありがとうございました。
このあと、希望される方には二次会もございます。
参加を希望される方は幹事までお声がけください。
それでは、お気をつけてお帰りください。」
| 場面 | フル例文のポイント |
|---|---|
| 開会 | 名前を名乗って安心感を与える |
| 新メンバー紹介 | 一人ずつ名前を呼び、短い挨拶を促す |
| ゲーム進行 | 「ぜひご参加ください」で参加を促す |
| 閉会 | 感謝の言葉と次の案内でスムーズに締める |
歓迎会を盛り上げる余興・ゲームアイデアと司会セリフ
余興やゲームは、参加者同士の距離を縮める大切な時間です。
ここでは、簡単に準備できて盛り上がりやすいアイデアと、それに合わせた司会セリフ例をご紹介します。
質問コーナーで自然な会話を広げる方法
新しい仲間への理解を深められるのが質問コーナーです。
シンプルな質問を用意しておけば、すぐに実践できます。
司会セリフ例
「ここで、新しい仲間についてもっと知るために質問コーナーを設けたいと思います。
質問はくじでランダムに引いていただきますので、どんな内容が出るかはお楽しみに。」
| 質問例 | アレンジ方法 |
|---|---|
| 休日はどんな過ごし方をしていますか? | ジェスチャーだけで答えてもらう |
| 最近はまっていることは? | 好きなキャラクターになりきって答える |
| 子どもの頃の夢は? | クイズ形式で他の人に当ててもらう |
自己紹介ゲームで緊張をほぐす工夫
自己紹介は形式的になりがちですが、ゲーム感覚を取り入れると盛り上がります。
「これから自己紹介をゲーム形式で行いたいと思います。」
「引いたカードに書かれたテーマに沿って自己紹介してください。」
| テーマ例 | 使い方 |
|---|---|
| 好きな食べ物 | ジェスチャーで表現 |
| 最近見た映画 | ワンフレーズで紹介 |
| 自分を動物にたとえるなら? | 動きをつけて説明 |
カルタ・クイズ進行用セリフ例
カルタやクイズ形式は誰でも参加できるのでおすすめです。
ポイントはシンプルなルールと短い進行にすること。
司会セリフ例
「ここからはカルタを使った自己紹介をしていただきます。
引いた札の文字を頭にして自己紹介をしてください。
たとえば『わ』なら『わたしの名前は~です』といった具合です。」
| ゲーム | 司会の一言 |
|---|---|
| カルタ自己紹介 | 「札を引いた文字で自己紹介をお願いします。」 |
| 早押しクイズ | 「正解だと思ったら挙手でお答えください。」 |
| チーム対抗○×クイズ | 「○と思う人は右、×と思う人は左に移動してください。」 |
準備を万全に!司会者のチェックリスト
司会をスムーズに行うには、事前準備がとても大切です。
ここでは、本番前に確認しておきたい項目をチェックリスト形式で整理しました。
進行表と台本の用意
進行表を作ることで全体の流れを俯瞰できます。
台本は「読み上げ用」と「メモ用」の2種類を用意すると安心です。
読み上げ用は丁寧に、メモ用は箇条書きで要点をまとめると本番中に迷いません。
会場・オンライン環境の確認
マイクやスクリーンなどの設備は、開始前に必ずテストしておきましょう。
オンライン参加者がいる場合は、音声・映像の接続チェックが重要です。
「声は聞こえていますか?」「画面は見えていますか?」と簡単に確認できるフレーズを準備しておくとスムーズです。
役割分担と二次会案内の整理
挨拶や乾杯の担当者、余興の担当者などを事前に押さえておくと進行が乱れません。
終了後に二次会がある場合は、その案内を誰がするかも決めておきましょう。
担当者と一度打ち合わせをしておくだけで当日の安心感が大きく変わります。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 進行表 | 全体の流れを時間ごとに整理 |
| 台本 | 読み上げ用とメモ用を作成 |
| 会場確認 | マイク・スクリーン・席配置を確認 |
| オンライン確認 | 音声・映像テスト、画面共有の準備 |
| 役割分担 | 挨拶・乾杯・余興担当を事前に調整 |
| 二次会案内 | 誰が案内するかを決めておく |
まとめ|司会者が楽しむことが成功の秘訣
ここまで、歓迎会の進行の流れや例文、準備のポイントを解説してきました。
最後に改めて大切なことをまとめます。
司会者が楽しむことが、会の雰囲気を決めます。
台本を用意し、進行表を確認しておけば大きな不安はなくなります。
もし進行が少しずれても、落ち着いて笑顔で対応すれば問題ありません。
参加者にとって印象に残るのは、完璧さよりも「温かい雰囲気」です。
司会者がリラックスして進める姿は、会全体を和ませる力を持っています。
自分も参加者の一人だと思いながら進めれば、自然と良い流れが生まれるでしょう。
| 成功の秘訣 | ポイント |
|---|---|
| 台本と進行表 | 事前準備で安心感を得る |
| 笑顔と声のトーン | 場を明るくし、安心感を与える |
| 柔軟な対応 | 進行がずれても落ち着いて調整 |
| 楽しむ姿勢 | 司会者が楽しむことで全体の雰囲気が良くなる |
あなたが安心して進めることで、参加者全員が心地よい時間を過ごせます。
準備を整え、笑顔で迎えれば、必ず成功に導けます。

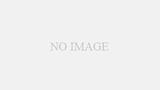
コメント