「残暑見舞いって、いつまでに出せばいいの?」
「どんな文章が正解なのかよくわからない…」
そんなお悩みを解決するために、本記事では残暑見舞いの正しい書き方・送る時期・日付表記・マナーをわかりやすくまとめました。
目上の方や友人、ビジネス相手など相手別の例文も豊富に紹介しています。
この記事を読めば、もう「どう書けばいい?」と迷うことはありません。
季節のご挨拶に心を込めて、ぜひ参考にしてください。
残暑見舞いとは何か?書く理由と意味
夏の終わりに届く「残暑見舞い」。これは単なる季節の挨拶にとどまらず、相手を思いやる気持ちを形にする、日本らしい美しい習慣です。
でも、「暑中見舞いとどう違うの?」「今どき送る意味ってあるの?」と思う方も多いかもしれませんね。
この章では、残暑見舞いの基本と、その背後にある心づかいの意味を、やさしく解説していきます。
暑中見舞いとの違いとは?
まず知っておきたいのが、「暑中見舞い」と「残暑見舞い」は送るタイミングが違うということ。
暑中見舞いは夏の最中に、残暑見舞いは立秋を過ぎてから送るのが基本です。
「立秋」とは、暦の上で秋が始まる日で、だいたい8月7日ごろを指します。つまり、
| 種類 | 送る時期 | 意味 |
|---|---|---|
| 暑中見舞い | 梅雨明け〜立秋前日 | 真夏の暑さをねぎらう |
| 残暑見舞い | 立秋〜8月末(遅くても9月初旬) | 秋口の暑さの中、相手を気遣う |
ポイントは、「暦の上では秋だけど、まだ暑い」時期に送ることです。
日中は暑くても、朝夕の風に少しずつ秋を感じ始めるこの時期こそ、残暑見舞いを通じて相手の体調や近況を思いやる好機なんですね。
なぜ今でも残暑見舞いが大切なのか?
現代ではLINEやメールで簡単に連絡が取れますよね。
それでもなお、はがきで残暑見舞いを送る人がいるのは、やっぱり「手紙という形で気持ちを届けたい」という温もりがあるからです。
特に、なかなか会えない相手や、日頃の感謝を伝えたい人にとって、残暑見舞いはちょっとしたギフトのようなもの。
たった一枚のはがきでも、想いはしっかり伝わる。それが残暑見舞いの魅力です。
また、ビジネスシーンでは、丁寧な印象を与えたり、関係性を深めるきっかけにもなります。
堅苦しいものでなくても大丈夫。言葉を選んで書かれた一通のはがきは、きっと受け取った人の心をじんわりと温めてくれるはずです。
残暑見舞いはいつ送る?正しい日付とタイミング
「残暑見舞いって、いつまでに送ればいいの?」という疑問は多くの人が持っています。
実は、残暑見舞いには正式な“送る時期”があるんです。
ここでは、2025年の暦に合わせた具体的なスケジュールや、「立秋」「晩夏」などの季語の意味と使い方を詳しく解説します。
2025年版|残暑見舞いを送る時期の目安
まず基本として、残暑見舞いは立秋(8月7日ごろ)以降から8月末までに届くように送るのがマナーです。
つまり、今年(2025年)のカレンダーにあてはめると…
| 日付 | 意味 | 対応する見舞い |
|---|---|---|
| 〜2025年8月6日 | 立秋前 | 暑中見舞い |
| 2025年8月7日〜8月31日 | 立秋〜処暑まで | 残暑見舞い |
| 9月1日以降 | 季節の節目を過ぎる | 送るのは控えた方が無難 |
重要なのは、「ポストに入れた日」ではなく相手に届く日が上記の範囲内になるようにすること。
郵便事情も考慮して、なるべく余裕をもって投函しましょう。
9月に入っても送っていいの?
9月に入ってしまったけど、まだ送ってない…。そんなときどうすればいいのでしょう?
結論から言うと、9月7日ごろの「白露」までならギリギリOKとされています。
ただし、それ以降になると「今さら感」や「マナー違反」と感じる方もいるので注意が必要です。
その場合は、「季節のご挨拶」として表現を少し変えるのも手です。
例えば「秋のご挨拶」として再構成すれば、失礼にはなりません。
「立秋」「晩夏」「葉月」の正しい使い方
残暑見舞いの締めくくりには、具体的な日付を使わず、季語を使うのが慣例です。
代表的な表現には、以下のようなものがあります。
| 表現 | 意味・使い方 |
|---|---|
| 令和七年 立秋 | 8月7日以降すぐに使うのに適した表現 |
| 令和七年 葉月 | 旧暦で8月を指す季語。8月中ならいつでも使用可能 |
| 令和七年 晩夏 | 夏の終わりを表す言葉。8月下旬〜末ごろにぴったり |
季語は、手紙に季節感を添えるだけでなく、日本語の美しさを感じさせるエッセンスでもあります。
和暦とセットで使うと、より品のある文章になりますよ。
残暑見舞いの書き方と基本構成
残暑見舞いを書くとき、どんな順番で、どんな内容を書けばいいのか迷いますよね。
でも大丈夫。基本の「型」を押さえておけば、あとは相手に合わせてアレンジするだけ。
この章では、文章の構成と文例のスタイルを解説しながら、使いやすい形に整理していきます。
文章の基本構成(あいさつ・本文・締め・日付)
残暑見舞いの文章は、大きく4つのパートで構成されます。
| パート | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① お見舞いの挨拶 | 「残暑お見舞い申し上げます」など | 句点「。」はつけず、やや大きめの文字で |
| ② 主文 | 時候の挨拶+相手への気遣い+自分の近況 | 相手の話が先、自分の話は後が基本 |
| ③ 結びの挨拶 | 健康を祈る一文で締めくくる | 「ご自愛ください」「お身体にお気をつけて」など |
| ④ 日付 | 「令和〇年 葉月」など季語を使った表現 | 縦書きなら漢数字、横書きなら通常の数字も可 |
この構成をもとに文章を組み立てれば、誰に送っても失礼のない文面になります。
まずは型を覚える。それが自然な文章への近道です。
目上の方・親しい人・ビジネス相手への文例の違い
残暑見舞いは、相手との関係性に応じて、言葉づかいや文調を調整するのがポイント。
| 送る相手 | 文調の特徴 | キーワード |
|---|---|---|
| 目上の方 | 丁寧語・敬語をしっかり使う | 「お伺い申し上げます」「お健やかにて」 |
| 親しい人 | ややカジュアルで親しみやすく | 「元気にしてる?」「また会いたいね」 |
| ビジネス相手 | かしこまりすぎず、でも誠実に | 「ご高配を賜り」「今後ともよろしく」 |
文例については、次章でたっぷりご紹介します。
ここでは、「誰に送るか」で文章の温度を変えることが大切だということを覚えておきましょう。
手紙とハガキ、どちらがよい?
残暑見舞いは基本的には「ハガキ」で送るのが一般的です。
手軽で親しみやすく、季節の絵柄入りハガキなどで視覚的にも楽しめるのが特徴ですね。
ただし、以下のような場合は「便せんで手紙として送る」のもおすすめです。
- 目上の方や恩師に丁寧に気持ちを伝えたいとき
- 長めの文章で報告やお礼をしたいとき
- フォーマルな場面で、より格式を重視したいとき
また、ビジネスで大量に送る場合は印刷でも問題ありませんが、一筆添えるとグッと丁寧な印象になります。
相手との関係性と状況に応じて、手段も柔軟に選びましょう。
相手別|すぐに使える残暑見舞いの例文集
ここからは、実際に使える「残暑見舞いの文例」をご紹介していきます。
相手との関係性によって、言葉の選び方や文章のトーンは少しずつ変えるのがポイントです。
それぞれのケースにぴったりな例文をまとめたので、コピペするだけでもOKですし、アレンジして自分の言葉にしても大丈夫ですよ。
目上の方・恩師向けの例文
敬語や格式を大切にしたい相手には、丁寧な表現が基本。
「見舞う」という言葉は目上の人には使わず、代わりに「お伺い申し上げます」を使うのがマナーです。
| 文例 | 使いやすい表現 |
|---|---|
| 残暑お伺い申し上げます。 厳しい暑さが続いておりますが、先生におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと拝察いたします。 私どももおかげさまで元気に過ごしております。 残暑厳しき折、何卒ご自愛のほどお願い申し上げます。 令和七年 立秋 |
「おかれましては」「拝察いたします」「ご自愛のほど」 |
友人や親しい相手へのカジュアルな文例
気心の知れた相手には、少しくだけた言葉づかいでOK。
夏の思い出や近況も気軽に書き添えると、ぐっと親しみが増します。
| 文例 | ポイント |
|---|---|
| 残暑お見舞い申し上げます。 立秋を過ぎたとはいえ、まだまだ暑い日が続いていますね。 〇〇さん、元気にしていますか? 私は先日、久しぶりに海に行ってリフレッシュしてきました。 季節の変わり目ですので、体調に気をつけてお過ごしくださいね。 また近いうちに会えるのを楽しみにしています。 令和七年 葉月 |
砕けすぎず、でも温かいトーンが◎ |
ビジネス関係・取引先向けのフォーマル文例
お世話になっている取引先や会社関係の方には、感謝と敬意をしっかり伝えることが大切です。
季節の挨拶とともに、日頃の御礼や今後の関係構築への前向きな姿勢も盛り込みましょう。
| 文例 | ポイント |
|---|---|
| 残暑お見舞い申し上げます。 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。 今後とも変わらぬお付き合いのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 残暑厳しき折、皆様のご健康とご発展をお祈り申し上げます。 令和七年 晩夏 |
丁寧語+感謝+健康祈願の三点セット |
相手に合わせた「ちょうどいい言葉づかい」を意識することが、好印象のカギになります。
残暑見舞いを書くときのマナーと注意点
せっかく丁寧に残暑見舞いを書いても、マナーを知らずに送ってしまうと逆効果になることも。
ここでは、最低限おさえておきたいポイントを整理しておきます。
特にビジネスや目上の方への挨拶では、ちょっとした気遣いが信頼につながるんですよ。
使う言葉や表現のタブー
残暑見舞いでは「忌み言葉(いまわしいことを連想させる言葉)」を避けるのがマナーです。
また、文章の調子が失礼にならないよう、以下の点に注意しましょう。
| NG表現 | 理由 | 代替案 |
|---|---|---|
| 残暑お見舞い申し上げます。 | 目上の人に「見舞う」はNG | 残暑お伺い申し上げます。 |
| ご苦労さまです | 上司に使うと失礼 | お疲れさまでございます |
| ますますご発展を祈っております。 | 命令口調に近い印象 | 心よりお祈り申し上げます |
相手との関係性に応じた敬語の使い分けが大切です。
手書きと印刷、どちらが丁寧?
気持ちが伝わるのはやっぱり手書き。
特に親しい相手や目上の方には、手書きの方が温かみがあって好印象です。
とはいえ、ビジネスなどで大量に送る場合は、印刷でも問題ありません。
その際は、ワンポイントでもいいので「手書きのひと言」を添えるのがおすすめ。
- 「いつもお世話になっております」
- 「今年も残暑が厳しいですね」
- 「またお会いできる日を楽しみにしています」
ちょっとしたひと言があるだけで、印象はグッと変わりますよ。
宛名や差出人の正しい書き方
最後に、うっかりやりがちな宛名面のミスについて。
ここを間違えると、どんなに文面が丁寧でも台無しになってしまいます。
| 項目 | マナーと注意点 |
|---|---|
| 住所 | 都道府県から省略せずに記載。番地も丁寧に。 |
| 数字 | 縦書きは漢数字(一、二、三)、横書きはアラビア数字(1、2、3) |
| 敬称 | 個人には「様」、会社には「御中」、医師・恩師には「先生」 |
| 差出人情報 | 自分の住所・名前・電話番号を明記 |
会社名は「(株)」などの略語ではなく「株式会社」と書くのがビジネスマナーです。
また、連名で送るときは、それぞれの名前に敬称をつけて丁寧に書きましょう。
まとめ|心を込めて季節のご挨拶を
残暑見舞いは、単なる季節の挨拶ではなく、相手を思いやる気持ちを形にした日本らしい心遣いの文化です。
形式やルールがあるとはいえ、大切なのは「相手を気にかけていますよ」という想いを丁寧に伝えること。
そのひと言が、暑さの中で少し疲れた心に優しく届くこともあるのです。
最後に、この記事でお伝えしたポイントを簡単におさらいしておきましょう。
| チェック項目 | ポイント |
|---|---|
| 送る時期 | 2025年は8月7日〜8月31日がベスト |
| 書き出し | 「残暑お見舞い申し上げます」「お伺い申し上げます」など |
| 構成 | あいさつ → 主文 → 結び → 季語の日付 |
| 季語の日付 | 「令和七年 立秋」「令和七年 葉月」「令和七年 晩夏」など |
| マナー | 敬語・宛名・手書きの一言など細部に配慮 |
残暑見舞いは、メールよりも一手間かかりますが、そのぶん「気にかけてくれたんだな」という気持ちがしっかり伝わる手段です。
特に、なかなか会えない人との距離を、そっと縮めてくれるのが魅力。
忙しい毎日だからこそ、手書きの一枚で季節を贈ってみませんか?
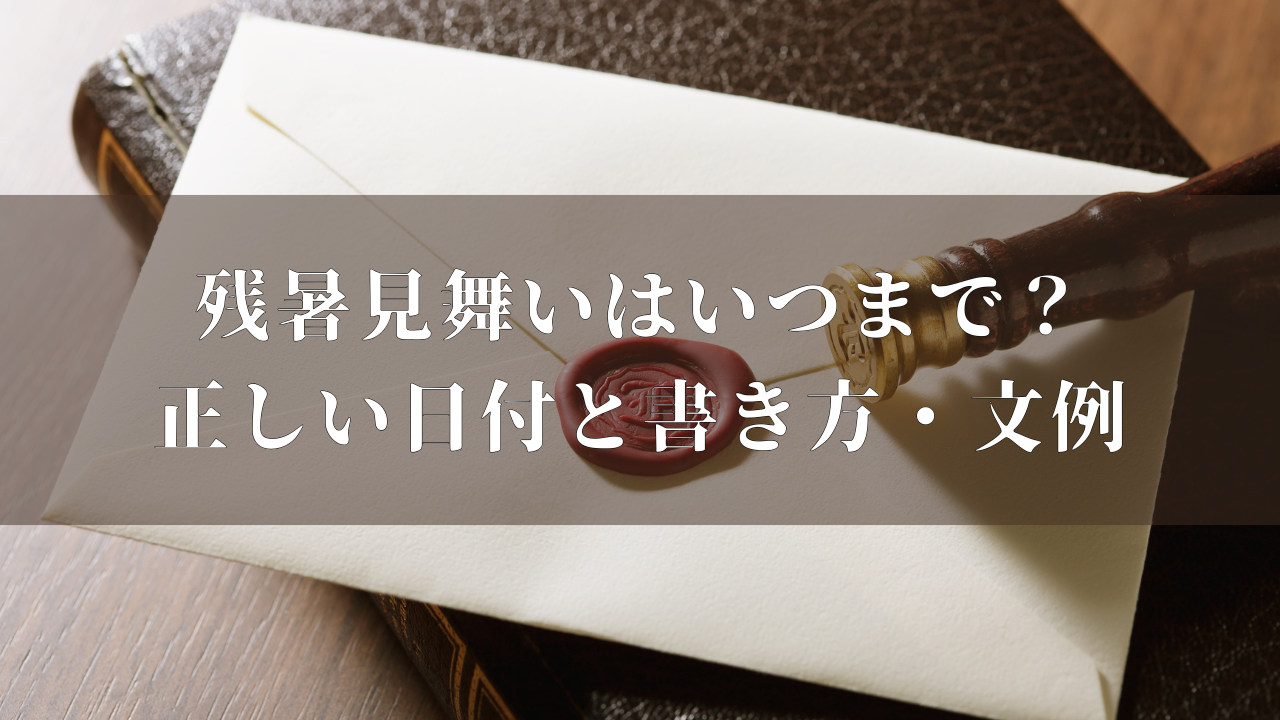
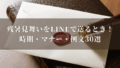
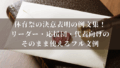
コメント